昭和43年(1968年)、私が高校生の時、父に「おまえこれ見るか?」と言われ一枚の映画のチケットを渡された。それが「2001年宇宙の旅」。私は気軽に「行くよ」と言ってそのチケットをもらい、全く何の予備知識も無く、一人、当時シネラマ方式大画面の映画館だったテアトル東京へ。
映画が始まる前は、イメージ的には宇宙戦争ものか、宇宙人でも出てくる冒険活劇のような今で言えばスターウオーズっぽい映画かと漠然と思いながら着席。
そうして上映開始・・ん?・・スクリーンに出てくるのは猿ばっかり。それも延々と続く。私は間違った映画館に入ってしまったのではないかと、チケットを見直す。ようやく、R・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」が鳴り響き、モノリス(見ているときはそれがなんなのか意味不明)が現れ、猿の放り投げた骨が宇宙船に・・。
これでやっと宇宙活劇開始か・・と思いきや、美しく青きドナウの音楽が流れる中、学者らしき男性が(今はなき)パンアメリカン航空のシャトルで宇宙ステーションへ・・。
そして宇宙ステーション→月面でのモノリス→木星への有人調査→HAL9000の反乱
と続き、ボーマン船長一人となり、ポッドに乗り込んで木星?へ。
そして突然現れる白い家具の部屋。年老いたボーマン船長。それに対比するかのように何かが生まれることを予感させる胎児。そうして再びツァラトゥストラが壮大に奏でられる。
当時高校生の私は、見ている間は、わくわくするでもなく、面白いでもなく、胸の中に今までに味わったことのない、なにかがモヤモヤとしているばかり。そのまま頭が混乱し、ボーッとして映画館をでました。
しかしその日から映画の様々なシーン、猿、モノリス、宇宙船、コンピュータ、そして何よりあの最後の数十分間が何を意味するのか・・哲学的とも思える疑問がずーっと私の頭の中占領することとなります。
驚くことにこの映画はアポロ11号の月着陸以前の作品なのです!デジタル技術を使ったSFXなどない時代に昨今のCGを駆使した現代の映画と変わらない(それ以上の)クオリティーの映像は驚異的!
そして今なお私に考えさせ続ける哲学的な問い。この映画は間違いなく私の人生の最高の映画です。
私は最近SF小説を書いていますが、この映画を見た体験がその根底にあることは間違い有りません。特に第一作「アインシュタインの神」で意識を持ったコンピュータネットワークが壊れてゆく場面はHALのシーンをオマージュしています。
映画の内容は、そのものを見るのが一番ですが、あの映画がどんな時代に作られたかを物語る資料として。以下に1968年公開時のプログラムから一部引用しました。(プログラム全ページの画像を乗せようと思いましたが、70年の著作権があるので断念。2038年に掲載予定?:生きていたらですが!)是非当時の時代の雰囲気を味わってください。
公開当時のパンフレットから引用
公開当時のパンフレット表紙 と 発行年月日



上のページに「2001年宇宙の旅でカブリックは数10年後に実際に行われていることを描いている」とあります。
2020年。現実になったこと、達成が難しいこと・・予想以上のこと・・。月着陸は東西冷戦で米ソがしのぎを削って、多額の予算が付いたという側面があるかもしれない。しかしそんなことがなくても、もしモノリスが発見されれば、世界が協力して探査をするドライブフォースになるかもしれない・・などと勝手に想像。
パンプレットの、保積善太郎氏(アストロ光学工業株式会社企画部長)による解説
「2001年宇宙の旅 人類はいま神秘の扉をひらく」より
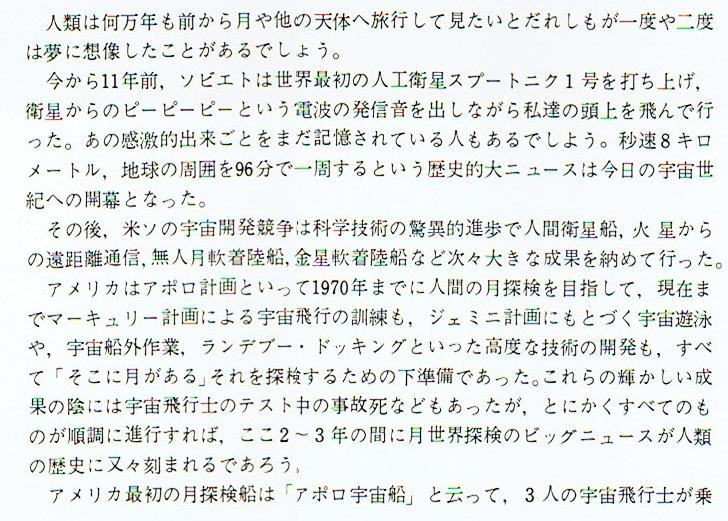

この文章から、この映画が作られた時代の雰囲気が少しは分かるかと思います。おそらく、若い方々はアポロの月着陸も自分が生まれるずっと前のこと。ポルノグラフィティーの歌う「僕らが生まれるずっとずっと前にはもう、アポロ11号は月に行ったっていうのに」(この曲すら1999年!)という感覚でしょうか。
この映画がそんな時代に作られ、今でも色あせないのは驚異としか言いようがありません。
スタンリー・カブリック(キューブリックでなく当時はこう記載されていた)の記事より
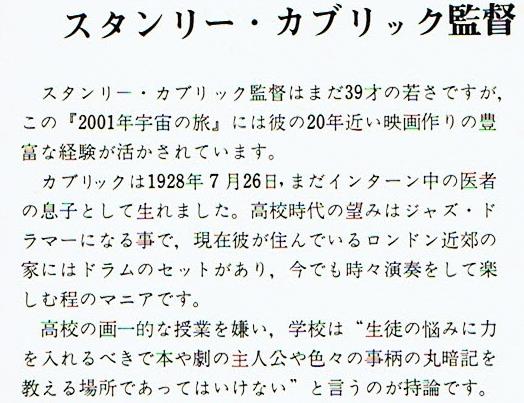

キューブリックはこの映画を作ったとき、まだ39歳の若さだという。大量破壊兵器に対する恐れ。当時は米ソ冷戦のまっただ中。ソ連が崩壊するなどは考えることすらできなかった。そんな時代に宇宙開発に望みをかけてこの作品は作られた。いやそれ以上に人類の未来を思っていたのではないでしょうか。
友人のコメントに「今まで見たことがない。とてもすばらしいといえる唯一の映画になるだろう」とのコメントが有りますが。その言葉は私にとっては、50年以上過ぎた今でも色あせることはありません。
まさに「2001年宇宙の旅」は芸術家が作った科学と空想の見事な結合作品 です。

コメントを残す